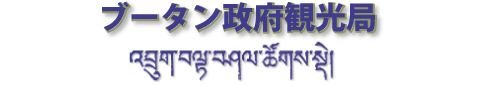国民総幸福量:ブータンの哲学の発展
これまで、世界中の経済学者が、幸福になるためには物質的な発展を遂げることが必要だと言ってきました。しかし、ブータンは物質的な成長を積むことが必ずしも幸福と結びつくわけではないと主張し、これまでの説とは別の方法で考えようとしてきました。ブータンは、これまでの概念に対して、その発展の度合いを測るのにGDP(Gross Domestic Product/国内総生産)ではなく、GNH(Gross National Happiness/国民総幸福量)を使っています。
第三代国王のジグミ・ドルジ・ウォンチュック陛下は、発展のゴールは『国民の繁栄と幸福』であるという考えを表しました。1971年にブータンが国連に加盟した際の国王のスピーチでは、『繁栄と幸福』が強調されました。この考えは、第四代国王のジグミ・シンゲ・ウォンチュック陛下がさらに練り上げ、彼は国王に就任した年に『我々の国の方針は、国や国民の為に経済的独立、繁栄、幸福を実現し国をまとめることだ』と語りました。
繁栄と幸福、両方が強調されていますが、幸福の方がより大切だとされています。第四代国王は、ブータンにとってはGDPよりもGNHの方が重要だと強調しました。GNHは今や世界中の様々の分野の専門家、学者、政府関連機関によって具体化されてきています。
第四代国王は、国家の問題が経済成長だけに特化されることを心配し、ブータンで優先するべきなのはGDPではなくGNHだと決めました。そして、国の発展の度合いをGNHで測ることを提唱しました。彼は、豊かであることが必ずしも幸せではないが、幸せであると段々豊かだと感じるようになる、と言っています。一般的な発展が、経済成長を最終目的として強調するのに対し、GNHの概念は、人間社会の発展とは、物質的な発展と精神的な発展が共存し、互いに補い合って強化していったときに起こるものだ、という考えに基づいています。
GNHの4つの柱とは
- 1.公正で公平な社会経済の発達
- 2.文化的、精神的な遺産の保存、促進
- 3.環境保護
- 4.しっかりとした統治
これらの柱は、国家や地域の価値、美学、精神的伝統を具体化しています。その結果、今や多くの他国が、ブータンに続いてGNHのコンセプトを取り上げています。このコンセプトによって、繁栄というものが、より広い意味で定義されました。GNHがより深く理解されるために必要なことは、まず、他国へ広く知られること、次に、たくさんの指標ができることによって物質的な利益も測れるようになること、そして最後に、経済方針の核として道徳と文化価値統合の必要が高まること、の3点があります。
発展のパラダイムとしてGNHを掲げることにより、ブータンは、その方針を地方にも浸透させ、発展の局面に取り込むことができるようになりました。地方の人々のニーズに答えたり、豊かな自然環境の促進、保全の必要が引き立たされたりしたからです。GNHの成功は、様々な地域で発展の局面にみることができます。数は少ないけれども高い重要性が置かれている観光業は、高い財源収入だけでなく、ブータンの文化価値の推進と保護の大きな手助けになっているのです。
更に、GNHのコンセプトにより、国家は発展すると同時に、人生哲学の核として幸福を促進することができるようになりました。政府から見ると、GNHは自給自足や貧富の差の減少を促し、政治を良くし、国民を強くしてきたのです。
2004年2月にはブータンでGNHの運用化に向けた国際会議が開かれました。参加国は、国際的な幸福のネットワークをつくり、ブータンの国境を越えてGNHが良い影響を及ぼせるようにするといいだろうと考えました。
このネットワークは、人々の幸福を反映した発展が続いているという、良い例を挙げようとしています。このネットワークは次の組織によって構成されています。
- Center for Bhutan Studies(ブータン)
- Spirit in Business(アメリカ、オランダ)
- Social Venture Network Asia(タイ)
- ICONS(ブラジル)
- Inner Asia Center for Sustainable Development(オランダ)
- The New Economics Foundation(UK)
- GPI(Genuine Progress Indicators)/GPI Atlantic(カナダ)
- Corptools/Values Center(アメリカ)
- International Society for Ecology and Culture(UK)